行政書士資格受験生あいちゃんの学習日誌:相続法改正
2020年06月07日 / 相続について/ 遺言書について
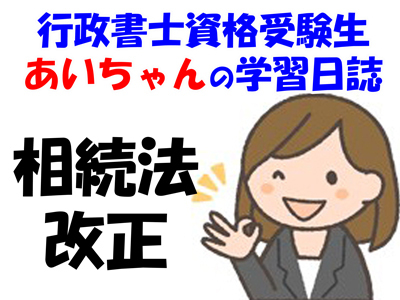

去年(2019年)は民法、特に相続法の大幅改正がありましたね。

小さな改正はすこしずつあったんだけど、去年のは約40年ぶりの大幅改正だったんですよね!

よく勉強されてますね!試験もこれからは改正民法をしっかり勉強しないといけませんね。

ところでどうして相続法が改正されたの?

難しい背景がいっぱいあるんだけど、簡単に言えばこれまでの相続法の小さな改正は子供に関することがほとんどで、配偶者のことはあまり重要視されていなかったんだ。しかし少子高齢化が進み、夫または妻に先立たれた一方の配偶者のことを保護する必要が高まったことで、今回の大幅改正に繋がったと言われているんだよ。

ふ~ん、で具体的に何がどう変わったの?

まずは大きな変更でいえば
①自筆証書遺言書の様式が緩和
②自筆証書遺言書の保管方法の追加
③10年より前の生前分与の取り扱い変更
④20年以上の夫婦間で家を贈与したときの取り扱い変更
⑤故人の配偶者に対する居住権の取り扱い変更
⑥相続権の無い者の特別寄与料が請求可能に
こんなところでしょう。
②以外は既に施行されているんだけど、2020年7月に満を持して②が施行されるんだ。

なんだか難しそうなものばっかり。私たち若い人に関係することは無いの?

ん~、相続法自体あんまり若い人たちには身近に感じることはできないかもしれませんね。でもこれから結婚を控えているあいちゃんにとっては⑥が大きく絡んでくるかもしれませんね。知っていて損はありませんよ!

そうなの?それじゃ⑥から詳しく教えて!

ハハハ、分かりました。でもその前に、いま一番ホットな話題の自筆証書遺言書の方から説明していこうと思うんだけどいいかな?

遺言書作成に関してはちょっと興味あるわ。でもあんまり難しい話はナシでお願いしますよ!

了解しました。なるべく簡単に説明していきますね!まずは①自筆証書遺言書の様式緩和について、次回詳しく説明していきます!

はーい!
行政書士金城勇事務所 ☜クリック
 098-923-1447
098-923-1447 Posted by 行政書士金城勇事務所 at
22:30
│Comments(0)
相続問題でよくある相談:会社を継ぐ人が決まっていない
2020年06月07日 / 相続:よくある相談
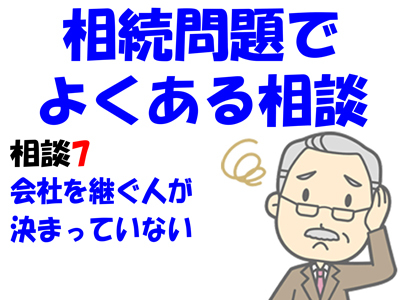
相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。
相談7 会社を継ぐ人が決まっていない
何が問題なのか?
・事業の継続に支障をきたしてしまうことも
・取引先に混乱を与えてしまうおそれがある
常に動いている会社(事業)には、一瞬たりとも”休憩”は許されません。オーナー社長に相続が発生したとしても、そのために従業員や取引先に迷惑をかけるわけにはいきません。
後継者問題で事業の継続に支障をきたし、それが長引くと信用問題等に発展してしまう可能性があります。一度失った信頼を回復するには時間がかかります。ましてや先代がカリスマ性を有していれば、なおさらマイナスからの船出となり、継承する人の重荷となってしまいます。会社(事業)には相続がないことを肝に銘じておくべきでしょう。
トラブルはこう回避する!
相続発生『前』なら・・・自社株承継対策を
事前に後継者を定め、後継者へ自社株がスムーズに継承されるよう遺言書を作成したり、相続時精算課税制度や納税猶予制度を活用し、自社株を贈与しておくべきでしょう。その際、会社の支配権を意識して、後継者が最終的に特別決議可能な議決権割合を確保できるよう配慮しておくべきでしょう。
また、市場流通性のない自社株を相続することによって後継者が負担する相続税納税資金の確保にも注意しておく必要があります。そのためには財産評価など、正確な現状把握が必要であり、税理士の協力が必要になります。
相続発生『後』なら・・・専門家と早めの対策を
税理士や弁護士などの専門家を交えて、会社の将来について話し合うべきでしょう。相続人が会社を継ぐのであれば、自社株の継承と納税資金の確保に全力を注ぎましょう。
一方、相続人が会社を継がない場合、相続した自社株を会社に金庫株として買い取ってもらう、M&Aで会社を譲渡する、MBOで社員に譲渡する、会社を清算する等、様々な選択肢について実現可能性を探らなければなりません。親族外承継を目指す場合、株価を上げる等の対策も検討しなければなりません。各分野の専門家を交えて、少しでも早く具体的に動く必要があるでしょう。
当事務所のHPもご覧ください。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
行政書士金城勇事務所 ☜クリック!
 098-923-1447
098-923-1447Posted by 行政書士金城勇事務所 at
09:00
│Comments(0)
相続問題でよくある相談:一部の子や孫だけにお金をあげている
2020年06月06日 / 相続:よくある相談
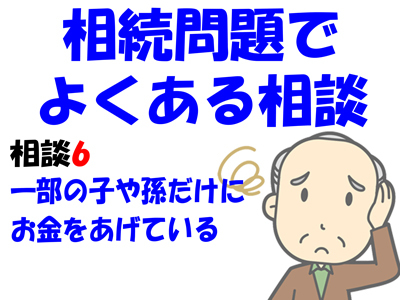
相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。
相談6 一部の子や孫だけにお金をあげている
何が問題なのか?
・不公平が争族を生むことも
・生前贈与が特別受益として相続財産に持ち戻されることも
一部の相続人や親族に偏った生前贈与や生活費の供与、学資の援助などをおこなっていると、不公平が争族を生む可能性があります。
相続人に対する贈与は特別受益(財産の前渡し)として遺産分割の際に考慮されるため、生前に多額の贈与を受けている相続人は、相続で何ももらえない、もしくはもらえても少しだけとなってしまう場合があります。
一方、相続人でない孫等に対する贈与は特別受益に該当しないため、偏った贈与を行っていると、孫のいる子と孫のいない子の間で世帯ベースでの取得財産額に不公平が生じ、法的に問題がなくても精神的にしこりを残してしまうことになります。
また、扶養義務者相互間における生活費や教育費は贈与税の課税対象ですが、前述同様、偏った援助が争族を生んでしまう可能性があります。
トラブルはこう回避する!
相続発生『前』なら・・・親族間で情報共有を
誤解を生むような贈与や援助は慎むべきですが、それが贈与者の気持ちであれば受け取らないのもおかしな話であり、実行する前に親族間で情報を共有しておくことをお勧めします。
また、どう話しても争族を回避できないと考えるなら、遺言に「持戻し免除」の条項を設け、かつ付言事項にその背景や信条を綴っておくと良いでしょう。
相続発生『後』なら・・・手がかりを探す
法的な問題と精神的な問題を分けて考える必要があります。
財産の提供が生活費や教育費といった「扶養」であれば、財産の前渡しとして遺産分割上それらを考慮したうえで話し合うことになります。これはあくまで法的な話であり、精神的には納得いかない相続人もいるでしょう。
また、受贈者等が相続人ではない場合、特別受益に該当しないため、不利益を被ったと主張する相続人がいても法的には対処しようがありません。
当事務所のHPもご覧ください。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 098-923-1447
098-923-1447Posted by 行政書士金城勇事務所 at
18:00
│Comments(0)
相続問題でよくある相談:財産に何があるのかよくわからない
2020年06月06日 / 相続:よくある相談

相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。
相談5 財産に何があるのかよくわからない
何が問題なのか?
・遺産が確定しない
・相続手続きが滞る
・相続税申告に支障をきたす
相続財産が確定しないと、相続税がかかるのかどうか、相続税の申告や納税が必要なのかどうか、判断できません。
また、そもそも相続財産に何があるのか、またその価値はいくらなのか確定しないと、遺産分割協議を進めることができません。申告期限までに相続財産が確定せず、未分割の状態で相続税の申告を行うので、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができず、高い相続税を負担することになってしまいます。
つまり、名義変更の事務手続きを含め、相続手続き全体が滞ることになるのです。
トラブルはこう回避する!
相続発生『前』なら・・・財産リストを作成
エンディングノートを活用し、どこに、何があるのか親に記載してもらっておく。
預けている金融機関について、金融機関名、支店名、住所や電話番号等の連絡先、担当者、取引内容等も記載しておいてもらうと相続人は楽になります。
遺言書に財産一覧を記載してもらう手もありますが、常に財産額や預け先が変動する場合、相続人が古い情報を鵜呑みにしてしまうリスクもあるため、エンディングノートやメモ等の活用をお勧めします。
その他、信頼できる人に通帳や財産明細を託したり、教えておく手もあるでしょう。
相続発生『後』なら・・・手がかりを探す
金融資産であれば、半年ないし1年に一度送られてくる「取引明細」や「年間取引報告書」等が来るのを待ちます。
不動産は、ありそうな自治体へ「固定資産の名寄帳」の交付を請求します。その際、先に死亡した祖父母や配偶者名義のままになっている可能性もありますので注意が必要です。また、道路等、固定資産税が課税されていない土地の漏れにも注意しましょう。
そのほか、自宅にカレンダーやティッシュ、ATM処理票、メモなどの手掛かりがないか、自宅の留守番電話に何かメッセージが残っていないか、探すしかありません。
当事務所のHPもご覧ください。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
行政書士金城勇事務所 ☜クリック!
 098-923-1447
098-923-1447Posted by 行政書士金城勇事務所 at
09:00
│Comments(0)
相続問題でよくある相談:分けることが難しい不動産や株式がある
2020年06月05日 / 相続:よくある相談
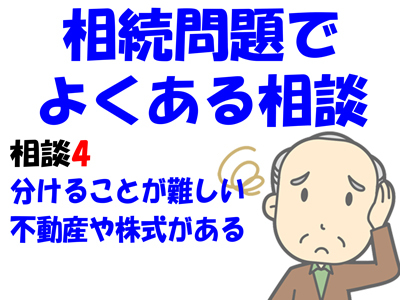
相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。
相談4 分けることが難しい不動産や株式がある
何が問題なのか?
・分割の方法や配分が難しい
・共有にすると最悪塩漬けになることも
・偏った遺産分割により争族を生む可能性がある
遺産分割の方法や配分が難しい。
分けられないからといって共有名義にしてしまうと、不動産であれば、将来建替えや売却などの際、共有者全員の足並みが揃わず、最悪塩漬け状態になってしまう可能性があります。また相続した子が死亡すると、その子(つまり孫)が相続することになり、従兄弟同士という親族関係が希薄した状況での共有になる可能性もあります。
共有を避け、誰かが単独で相続すると、偏った遺産分割となり、争族を生むきっかけとなってしまうかもしれません。
なお、株式は準共有(権利行使者の指定は持分に従いその過半数で決する)となり、会社運営に支障をきたす恐れもあります。
トラブルはこう回避する!
相続発生『前』なら・・・遺留分の侵害に注意
遺言書を作成し、分けにくい財産を相続人Aに単独で相続させ、そのうえで相続人Bに遺留分を侵害しないよう他の財産を相続させるという手があります(遺留分について詳しくはこちらを参照ください)。
分けにくい財産しかない場合、生命保険金の受取人をAと指定し、Aは財産を相続する代償としてBへその保険金を活用し代償金を交付するという手もあります。
なお、相続税は相続税評価額(路線価等)で計算しますが、遺産分割における話し合いの基準は時価です。代償分割を採用する場合でも、評価額と時価に剥離があると思わぬ額の資金が必要になりますので注意が必要です。
相続発生『後』なら・・・換価分割も視野に!
遺産分割の優先順位は
①現物分割
②代償分割
③換価分割
④共有分割
となります(それぞれの分割について詳しくはこちらを参照ください)。現物分割が難しい場合、Aに代償金を交付できるだけの財産があれば良いのですが、代償分割も無理であれば換価分割も視野に入れなければならないでしょう。
なお、家庭裁判所で調停や審判等になった場合、原則として代償金の分割払いは認められず、代償金を一括で払うことが可能であることを示す必要があります。
当事務所のHPもご覧ください。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
行政書士金城勇事務所 ☜クリック!
 098-923-1447
098-923-1447Posted by 行政書士金城勇事務所 at
09:00
│Comments(0)
相続問題でよくある相談:親のめんどうを見ている子と見ていない子がいる
2020年06月04日 / 相続:よくある相談
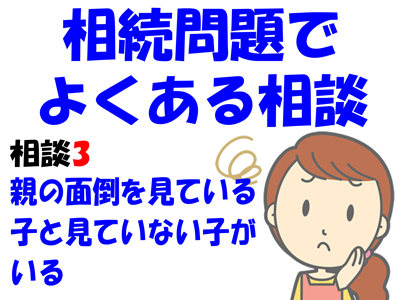
相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。
相談3 親の面倒を見ている子と見ていない子がいる
何が問題なのか?
・介護の貢献度で揉めることがある
・「寄与分」の勘違いが火種になることがある
・使い込みを誤解されることがある
親の介護等への貢献度を巡り、相続に発展する可能性があります。
親の面倒を子が見るのは扶養義務として当然のことであり、そこに寄与分は原則発生しません。親の面倒を全く見ない子がいたとしても、だからといって面倒を見た子に寄与分は発生しません。子として当然の行為と法律は解釈しているからです。
もちろん、その貢献が扶養義務を超えた相当な負担であれば寄与分が発生すると考えられますが、仮に寄与分が発生したとしても、その割合は当人が期待する水準以下であることがほとんどであり、満足を得るレベルには至らないでしょう。
また、面倒を見ていない子から、介護負担の旗の下、親の財産を指摘に流用していると誤解を受ける場合もあります。
トラブルはこう回避する!
相続発生『前』なら・・・介護活動を記録する
親の面倒を見ることについて、子供同士で話し合うべきです。
労務だけでなく、経済的な負担、精神的な負担等についても情報を開示し、何がどの程度負担なのか、将来担った負担を誰がどのように清算するのかなど、ある程度合意しておくことが望ましいです。
日記や介護ノート等に日々の活動を記録しておくと、後日客観的な資料として有効です。面倒を見ていない子に説明する際にも、理解を得やすいでしょう。
また親と子の財産を分別管理することはもちろん、親のために使用したお金の領収証やレシートは残し、通帳にも何に使用したかメモしておいたほうが良いでしょう。
親に遺言書を作成してもらう、あるいは生命保険の受取人を面倒を見た子だけにするなども有益な方法です。
相続発生『後』なら・・・客観的な資料を示す
介護負担の程度を客観的に示せる資料を先方へ提示し理解を得るしかありません。親の面倒を見たからといって法的に寄与分が発生しないことを理解したうえで、冷静に話し合うべきでしょう。
当事務所のHPもご覧ください。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
行政書士金城勇事務所 ☜クリック!
 098-923-1447
098-923-1447Posted by 行政書士金城勇事務所 at
09:00
│Comments(0)
あまりにも偏った遺産配分がされそうなときは
2020年06月03日 / 相続について
 もしあなたの父が遺言書に
もしあなたの父が遺言書に「全財産を愛人の〇〇に遺贈する」
と遺していたら、あなたを含めた遺族はどう思いますでしょうか。
「こんな遺言なんて無効に決まってるでしょ!」
と普通は思いますよね?
しかし遺言書の形式に問題が無ければ、その遺言は一応有効となります。
それなら遺族は、大切な遺産を愛人に全て持っていかれるのを黙って見過ごすしかないのでしょうか。
そんなことはありません。一定の法定相続人には、偏った遺産配分がされそうな場合に、最低限取り戻せる遺産の割合が法定されています。そのことを「遺留分」といいます。
また冒頭の例では被相続人の愛人に全財産を遺贈するというものですが、遺族内で偏った配分の遺言がされたときにも遺留分の請求ができます。
ただし遺留分は黙っていても保障されるというわけではなく、「遺留分侵害額請求」を主張することにより、はじめて確保されます。
それでは遺留分について詳しくみていきましょう。
【遺留分権利者】
遺留分は、被相続人の意思を覆すような非常に強い権利です。したがって全ての法定相続人に認められているわけではありません。
認められている者:配偶者、被相続人の子や孫等(直系卑属)、被相続人の両親等(直系尊属)
認められていない者:被相続人の兄弟姉妹
一応、遺産相続順位三位に被相続人の兄弟姉妹が法定されていますが、法律上兄弟姉妹は被相続人との関係性は低いとみなされ、遺留分までは認められていません。
【遺留分の割合】
それでは遺留分の請求をした場合、どのくらいの割合で戻ってくるでしょうか。
これは一部例外がありますが、法定相続分の半分と考えて頂いて問題ありません。

このイラストのケースですと、法定相続分は妻:2分の1、子AB共に4分の1となります。遺留分は法定相続分の半分(2分の1)ですので、
遺留分割合
妻:4分の1
子A:8分の1
子B:8分の1
以上の割合で遺産を取り戻せることになります。
ここで、妻・子A・子Bの取り分を足し算すると2分の1になることがわかりますよね?(4分の1+8分の1+8分の1=2分の1)では残りの2分の1はどこにいくのでしょう?
そうです。
残りの2分の1は遺言者の意思が尊重され、愛人にいってしまいます。
どんなに偏った配分の遺言であっても、遺言者の意思はある程度尊重されるべきと法律は考えているのですね。
【遺留分の請求】
あまりに偏った相続配分がされそうなとき(遺留分が侵害されそうなとき)、遺留分の権利を主張するかどうかは個人の自由です。
「被相続人が考えたことだからやむを得ない。そのまま従う」と考えて遺留分を放棄するのも自由ですし、
「いや、納得がいかない!いくら被相続人が考えたことでも遺留分に相当する財産はどうしてももらう!」と考えるのも自由です。
遺留分の権利を主張する場合
①遺留分侵害額請求
遺留分の権利を主張することを「遺留分侵害額請求」といいます。この遺留分侵害額請求をすることによって、法定された遺留分を取り戻すことが可能となります。
②遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求は、特別な手順を踏まなくても、相手方に意思を表示するだけで足りるとしています。つまり裁判所を通して主張する必要はありません。
ただし、遺留分侵害額請求は1年以内にしなければなりませんので、通常は遺留分侵害額請求をしたことを証拠として残すため、内容証明郵便を使用することがほとんどです。
③遺留分侵害額請求の期間
遺留分侵害額請求は、遺留分が侵害された者が
「相続の開始されたことを知ったときから1年を経過したとき」
および
「遺留分を侵害された贈与または遺贈があったことを知ったときから1年を経過したとき」
または
「相続開始のときから10年を経過したとき」
に消滅します。
まとめ
遺された家族が遺産を巡って争うのは誰も望んでいません。
これから遺言書を作ろうと思っている方は、遺留分をしっかり理解したうえで、遺産配分を考えましょう。もしどうしても遺留分を侵害してしまうような配分をしたいときは、遺言書の付言事項でしっかり自分の意思を伝えることです。
そして普段から家族とコミュニケーションを取り合い、家族の役割を理解してもらうことが大切です。
遺された家族が【争族】とならないために、まずは家族で話す機会をもつことから始めてはいかがでしょうか。
当事務所のHPもご覧ください
↓ ↓ ↓ ↓
行政書士金城勇事務所 ☜クリック!
 098-923-1447
098-923-1447Posted by 行政書士金城勇事務所 at
09:00
│Comments(0)
法定相続分:さまざまなケース
2020年06月02日 / 相続について
 前回のブログでは法定相続の基本的な考え方を説明しましたが、今回はさまざまなケースでの法定相続割合を見ていきましょう。知っていて損は無いですよ!
前回のブログでは法定相続の基本的な考え方を説明しましたが、今回はさまざまなケースでの法定相続割合を見ていきましょう。知っていて損は無いですよ!【再婚している場合】

現妻とのあいだの子と前妻とのあいだの子に、法定相続割合の違いはありません。どちらも被相続人の直系卑属にあたりますので、このイラストの例だと妻と子供3人の通常の振り分けになります。
現妻:2分の1
子A:6分の1
子B:6分の1
子C:6分の1
当然ではありますが、前妻には相続権はありません。
【養子縁組をしている場合】

養子は法律上実子とみなされますので、実子と同じ相続分を持つことになります。
ただしここで注意してほしいのは、配偶者の連れ子は養子ではありませんので相続分はありません。もし配偶者の連れ子にも相続させたい場合は、正式に養子縁組の手続きを踏むことが必要になります。もちろん配偶者の連れ子であれば、何人養子縁組しても全員に法定相続人に地位が与えられます。
そして養子には「普通養子」と「特別養子」がありますが、普通養子は前の親との縁は切れませんので、養子は前の親と現在の親との2つの相続権を有します。このイラストの例だと、養子Cは妻の前夫の遺産も現親の遺産も両方の相続権を持つことになります。
妻:2分の1
実子A:6分の1
実子B:6分の1
養子C:6分の1
【婚姻外の相手との子がいる場合】

「嫡出子(ちゃくしゅつし)」とは婚姻中の夫婦から生まれた子をいい、「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」とは婚姻外の男女から生まれた子をいいます。嫡出子も非嫡出子も相続配分に違いはありませんので、通常の相続割合で計算されます。
妻:2分の1
嫡出子A:6分の1
嫡出子B:6分の1
被嫡出子C:6分の1
※以前の民法では「非嫡出子の相続分は嫡出子の半分である」と規定されていましたが、非嫡出子の子は自分自身が望んで婚姻外の男女から生まれた訳ではなく、それをもって嫡出子との身分を区別されるのは不合理な差別であると違憲判決がなされました(平成25年9月4日)。この判決を受け改正民法(平成25年12月11日公布・施行)ではこの規定が削除されております。
【兄弟間に異母(異父)兄弟がいる場合】

相続順位三位の兄弟姉妹間で相続が起きる場合に、被相続人の父と母を同じくする兄弟姉妹(イラストの例だと全血兄弟A)と、父と母のどちらか一方だけを同じくする兄弟姉妹(イラストの例だと半血兄弟BC:俗にいう異母兄弟)は、いずれも相続人になりますが、半血兄弟の法定相続分は全血兄弟の法定相続分の2分の1です。
少し計算がややこしくなりますが、全血兄弟Aの相続割合は【2/2+1+1】で2分の1、半血兄弟B・Cはそれぞれ【1/2+1+1】で4分の1となります。
全血兄弟A:2分の1
半血兄弟B:4分の1
半血兄弟C:4分の1
このケースは被相続人に親も子供もいない場合に発生します。民法上で兄弟間に差別を設けるという特殊なケースですが、覚えておいて損はありません。
【相続人が被相続人より先に亡くなっていた場合】

上のイラストの場合、本来6分の1の相続を受けるはずであった子Cが、被相続人より先に亡くなっていた場合は、そのままCの子DEが代襲して相続分を受け取ることになります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。また被相続人よりも先に子・孫が先に死亡していた場合は、さらにそのひ孫へと相続が移っていきます。このように、亡くなった人の財産は子→孫→ひ孫→玄孫・・・と、本来相続するべき人が亡くなっていたらどんどん下の世代に相続されていくのが代襲相続の基本です。
妻:2分の1
子A:6分の1(1/2×1/3)
子B:6分の1
孫D:12分の1(1/2×1/3×1/2)
孫E:12分の1
代襲相続は第三順位の兄弟姉妹の相続時にも適用されますが、この場合は兄弟姉妹の子までが代襲相続の範囲となっており、兄弟姉妹の孫から下の世代には相続配分はありません。
【相続を放棄した者がいる場合】

相続放棄をした場合は、最初から相続人とならなかったものとみなされます。したがって孫DEにも代襲相続は発生しません。
妻:2分の1
子A:4分の1(1/2×1/2)
子B:4分の1
子C:なし(相続放棄)
孫D:なし(Cの相続放棄)
孫E:なし(Cの相続放棄)
相続放棄と似たものに、「相続欠格」と「相続廃除」がありますが、これらは代襲相続が適用され下の世代へと相続配分が移っていきます。相続放棄は自らの意思により相続をしないとしたものに対し、相続欠格と相続廃除は自らの意思とは関係なく相続権を外されるものであり、その下の世代には何の落ち度もないからです。
一応基本的なことは説明しましたが、各家庭によってまだまだ複雑なケースが発生する場合もあります。
皆様のご家族がどう当てはまるのか、しっかり確認しておいて下さいね!
当事務所のHPもご覧ください
↓ ↓ ↓ ↓
行政書士金城勇事務所 ☜クリック!
 098-923-1447
098-923-1447Posted by 行政書士金城勇事務所 at
09:00
│Comments(0)
法定相続分:相続順位と遺産配分
2020年06月01日 / 相続について
 大切な人が亡くなった後、亡くなられた方が遺言書を遺していたのであれば、基本的にはその遺言書通りに遺産を配分していくことになります。
大切な人が亡くなった後、亡くなられた方が遺言書を遺していたのであれば、基本的にはその遺言書通りに遺産を配分していくことになります。しかし残念ながら現状ほとんどの方は遺言書を遺していません。そんなときは遺族が集まって遺産をどう分けていくか家族会議が行われたりするのですが、これを遺産分割協議といいます。
この遺産分割協議ですんなり話がまとまればいいのですが、なかなかそう簡単にはいかないもので、どんなに仲の良かった兄弟でも偏った遺産配分がなされそうなときは、自己の取り分を主張して喧嘩別れに終わってしまうことは多々あります。
さて、ここでひとつ疑問が生じます。
「偏った配分といっても遺族全員平等に分けないといけないの?」
そうですよね。亡くなられた方の配偶者、子供、両親等が、全員平等の遺産配分というのはおかしいような気もします。
そこで民法では、遺産を貰える親族の範囲、遺族の相続順位、遺産の取り分を法律で定めました。それが法定相続分です。
もちろん不動産などの遺産は細かく分けることはできませんので、遺産を法定相続分きっちりと振り分けることは不可能ですが、実際のところはこの法定相続分を念頭に置きながら、お互いの妥協点を探っていくという形となります。もちろん遺族全員が納得すれば法定相続分とは違った配分をすることも問題ありません。
これからその法定相続分について説明していきす。またこの法定相続分は相続税を計算するうえで必ず必要となる知識です。ご自分の家族に当てはめてしっかり予習しておいてください。
【法定相続分】
配偶者

まず被相続人(亡くなられた方)の配偶者は、必ず相続人になります。
もしこの夫婦に子供もいない、旦那様の両親も既に他界、旦那様に兄弟姉妹もいないということであれば、遺産は全額奥様が受け取ることになります。
このあと相続順位について説明していきますが、基本的に遺産配分は【配偶者と〇〇】という形で、この〇〇の部分に相続順位が発生するということです。
被相続人の配偶者は、被相続人と苦楽を共にし一緒に財産を築きあげてきたという考えから、民法では被相続人=配偶者という特別な地位を与え配偶者を保護しているのです。
第一順位

相続順位の第一位は夫婦の子供(直系卑属)です。
遺産の配分は、遺産総額の半分を配偶者が取得し、残りの半分を子供たちで平等に分ける形になります。
このイラストの例だと遺産配分は、
配偶者が2分の1で、残りの2分の1を子供2名で平等に分けるので子A・子B共に4分の1の配分になります。
配偶者:2分の1
子A:4分の1
子B:4分の1
なお、被相続人にご両親や兄弟姉妹がいたとしても、子供が一人でもいたのならそこで相続は終了であり、両親や兄弟姉妹は遺産を請求できません。
また、イラストの例で既に配偶者も亡くなっているのであれば全額子供が遺産を受け取ります。
第二順位

相続順位の第二位は被相続人の両親(直系尊属)です。
この夫婦に子供がいないとき、はじめて第二順位という概念が発生します。
遺産の配分は、遺産総額の3分の2を配偶者が取得し、残りの3分の1をご両親で分ける形になります。
このイラストの例だと遺産配分は
配偶者が3分の2で、残りの3分の1を両親2名で平等に振り分けるので父・母共に6分の1の配分になります。
配偶者:3分の2
父:6分の1
母:6分の1
なお、被相続人に兄弟姉妹がいたとしても、ご両親のうち1人でもご健在であればそこで相続は終了であり、兄弟姉妹は遺産を請求できません。
また、イラストの例で既に配偶者も亡くなっているのであれば全額両親が遺産を受け取ります。
第三順位

相続順位の第三位は被相続人の兄弟姉妹です。
この夫婦に子供やご両親がいないとき、はじめて第三順位という概念が発生します。
遺産の配分は、遺産総額の4分の3を配偶者が取得し、残りの4分の1を兄弟姉妹で分ける形になります。
このイラストの例だと遺産配分は
配偶者が4分の3で、残りの4分の1を兄弟姉妹2名で平等に振り分けるので兄・妹共に8分の1の配分になります。
配偶者:4分の3
兄:8分の1
妹:8分の1
また、イラストの例で既に配偶者も亡くなっているのであれば全額兄弟姉妹が遺産を受け取ります。
以上が基本的な法定相続の順位と配分の考え方です。
次回からは法定相続分の特別なケースについて説明していきます。
当事務所のHPもご覧ください
↓ ↓ ↓ ↓
行政書士金城勇事務所 ☜クリック!
 098-923-1447
098-923-1447Posted by 行政書士金城勇事務所 at
12:34
│Comments(0)
秘密証書遺言について
2020年05月29日 / 遺言書について

前回までは自筆証書遺言、公正証書遺言について説明してきました。
今回の第3回目は秘密証書遺言について説明します。
【秘密証書遺言】
特長
これまで説明してきた自筆証書遺言と公正証書遺言の欠点を補った方式がこの秘密証書遺言といえます。なので最も採用されている方式なのと思いきや、実は全くと言っていいほど採用されておりません!
私の知り合いの行政書士はこの秘密証書遺言の作成に何件か携わってきたそうですが、「沖縄で一番多く秘密証書遺言作成のサポートしているのは僕だ!」と豪語しておりました。個人的には使い勝手がよく、もっと採用されていても良いと思っているのですが、中途半端なイメージがあるのでしょうか、なぜか採用率は非常に低い方式です。
前置きが長くなりましたが、特長について説明しましょう。秘密証書遺言とは遺言書そのものの方式ではなく、いわば遺言書を秘密に保管するための方式、すなわち、遺言書が封入されていることを公正証書の手続きで公証しておくというものです。したがって、遺言の文言は自筆である必要はなく代筆でもワープロで打ったものでも構いません。これは遺言者にとって最も大きなメリットといえます。自筆証書遺言の全文自筆という要件は最も高いハードルでしたが、これが代筆でも良いとなると字が書けない年配層の遺言者にとっては安心して作成に取り組むことができます。さらに内容を公証人に口述する必要もないので、公証人に支払う手数料が安くすむメリットがあります。
秘密証書遺言の要件は次のとおりです。
・遺言者の署名
・遺言者が封書を封入、証書と同じ印章で封印
・証人2人以上の立会いの下で、この封書を公証人に提出し、これが自分の遺言書であること、証書を書いた者の氏名・住所を申述
・公証人が、遺言者の申述と日付を封紙に記載し、遺言者・証人・公証人が署名・捺印
以上の方式に従って証書が作成された旨を、公証人が付記して署名押印という手続きで作成されます。
なお秘密証書遺言は、秘密証書遺言としては無効でも、自筆証書遺言としての要件が備わっていれば自筆証書遺言として認められます。
長所と短所
長所
・遺言者の署名と捺印が要求されているだけなので、代筆やワープロにより作成されたものでもよく、書面の作成が容易であること。
・証人に遺言の内容がわからないため、秘密が保たれること。
・公証人の手数料が安価であること。
短所
・原本が遺言者に渡されるため保管について注意しなければならないこと。
・遺言の内容については公証人が点検しないため無効となるおそれがあること。
前回・前々回のブログで自筆証書遺言と公正証書遺言について説明しました。今回の秘密証書遺言を含めた3種類の遺言方式についてメリット・デメリットはご理解できましたでしょうか。
もし遺言書を書きたいと思い、どの方式で作成するか迷ったときは、いつでも私にご相談下さい。皆様に最適な方法でサポートさせて頂きます。
当事務所のオリジナルHPもご覧下さい
↓ ↓ ↓ ↓
行政書士金城勇事務所 クリック!
Posted by 行政書士金城勇事務所 at
20:10
│Comments(0)
公正証書遺言について
2020年05月28日 / 遺言書について

前回のブログでは普通方式遺言の自筆証書遺言について記載しました。
第二回目の今回は公正証書遺言です。
【公正証書遺言】
特長
現時点で最も安全性と確実性が高い方式といえます。自筆証書遺言が基本的に一人で誰にも内緒で作成するというものでしたので、要件が整わない場合は無効になる恐れがあるのと、自己管理が基本となるので紛失や偽造の恐れがあること、さらに誰にも内緒で作成するので遺言の存在自体が知られない、または発見されない可能性等がありました。その短所を補ったのがこの公正証書遺言です。
公正証書遺言は遺言者が証人2人と共に公証役場に行って、遺言内容を口述し公証人が作成します。外出できない状態のときは公証人が出張してくれます。
公正証書遺言の作成手順は次のとおりです。
・証人2人以上の立会い・言者が、遺言の趣旨を公証人に口述
・公証人が遺言者の口述を筆記した内容を遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させる
・遺言者と証人は、筆記の正確なことを承認したうえ、各自これに署名捺印
以上の方式に従って証書が作成された旨を、公証人が付記して、署名捺印という手続きで作成されます。
なお、①未成年者、②推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族、③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および雇人は承認になることができません。
長所と短所
長所
自署が要件とされていないので文字が書けない者でも作成することができる。
原本が公証役場に保管されるので保管という意味では最も安全確実といえること。
短所
2人以上の証人の立会いが必要なので内容を秘密にしておけないこと。
遺産の価格やその内容に応じて公証人の手数料が決まるので遺産が多い場合には費用が高くなること。
では実際に費用はいくらくらいかかるのかというと、
①公証人への手数料
遺言者に書く財産の価格が
100万円まで・・・5000円
200万円まで・・・7000円
500万円まで・・・11000円
1000万円まで・・・17000円
3000万円まで・・・23000円
5000万円まで・・・29000円
1億円まで・・・43000円
となります。
手数料は遺産を譲り受ける人ごとに計算し、合計します。
更に遺産総額が1憶円未満の場合は11000円加算されます。
例を挙げると
遺言者が妻に3000万円、長男に1000万円、長女に500万円を相続させる遺言を書いた場合
妻の分:手数料23000円
長男の分:手数料17000円
長女の分:手数料11000円
遺産総額1憶円未満:手数料11000円
合計:62000円
となります。
②証人2名
日当1人あたり:相場10000円
計20000円
ただし知り合いに証人を頼めば、無料でお願いすることもできますが、知り合いに証人を引き受けさせるのは気が引きますし、情報が家族に漏れないとも限らないので、証人は第三者に頼むのが理想かもしれません。
以上、①と②により、上記の家族の例だと82000円程度かかることになりますが、実際は公証人との事前打ち合わせや書類の収集など、専門的な知識が必要となるので、多くの方は行政書士へ作成サポートを行ってもらうことになります。行政書士のサポート費用は各事務所によって異なりますので一概にはいえませんが、公正証書遺言の作成費用はトータル15万円から20万円程度見積もっておいたほうが良いでしょう。
自分の死後、遺された家族がいつまでも仲良く幸せに暮らしていけるために、大きな安心を得るという意味で20万円の遺言書作成費用は、私は決して高くはないとみますが、皆様はどう感じましたでしょうか。
次回は3つ目の遺言方式秘密証書遺言について説明します。
当事務所オリジナルHPもご覧ください
↓ ↓ ↓ ↓
行政書士金城勇事務所 クリック!
Posted by 行政書士金城勇事務所 at
13:15
│Comments(0)
相続問題でよくある相談:相続人の仲が悪い
2020年05月27日 / 相続:よくある相談

相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。
相談2 相続人の仲が悪い
何が問題なのか?
・遺産分割が成立しづらい
・相続手続きが滞るおそれがある
・相続税の軽減措置が受けられないことがある
相続人が不仲だと、遺産分割協議が成立しない可能性があります。
相続税の申告及び納税は、たとえ遺産分割に合意できなかったとしても、期限の延長は認められません。その場合、未分割の状態で申告せざるを得ず、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を受けることができません。つまりかなり高い相続税を納税することになってしまうのです。
また、預貯金ももちろん遺産分割の対象であるため、相続人全員の足並みが揃わない限り、金融機関は相続人の預貯金の払い出しには応じてくれず、結果、相続人自身で納税資金を調達しなければなりません。
さらに預貯金に限らず不動産等すべての名義が被相続人のままになり、売却や立替え等も一切できない状態が続くことになります。
トラブルはこう回避する!
相続発生『前』なら・・・まずは話し合いを
少し仲が悪いだけなのか、それとも数年間口をきかないほど不仲なのかによって対応が異なりますが、まずは家族で話し合うことをおすすめします。争続の原因は家族間のコミュニケーション不足によることが多いのです。
すでに話し合いで解決できるレベルでないほど不仲である場合は、遺言書を作成するべきでしょう。
相続発生『後』なら・・・弁護士を交えた協議も
不仲であっても、まずは当事者同士で話し合うしかありません。
当事者同士での話し合いが無理なら、弁護士を介して話し合うことになります。相続人の配偶者や親戚等を交えて話し合いを進める場合もありますが、外野の口出しによってかえって揉めるケースもありますので、そこは慎重に検討するべきです。
弁護士を交えても協議が成立しない場合、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。いきなり裁判をしようと思っても、家庭裁判所ではまず調停を勧め、調停が不調に終わった場合、審判に移行することが多いです。
当事務所のHPもご覧ください。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
行政書士金城勇事務所 ☜クリック!
 098-923-1447
098-923-1447 Posted by 行政書士金城勇事務所 at
19:55
│Comments(0)
料金一覧
2020年05月27日 / 料金一覧

【相続相談】
5,000円~
【遺言書作成サポート】
60,000円~
【遺産分割協議書作成】
50,000円~
【法定相続一覧図作成】
20,000円~
【遺言執行手続き】
300,000円~
その他なんでもご相談ください。
Posted by 行政書士金城勇事務所 at
17:04
│Comments(0)
相続問題でよくある相談:相続人に長い間連絡が取れない人がいる
2020年05月26日 / 相続:よくある相談
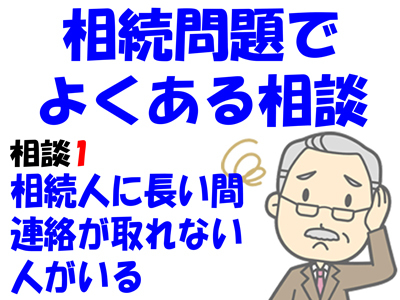
相続の問題を扱う上で、よく受ける相談についてご紹介していきます。
相談1 相続人に長い間連絡が取れない人がいる
何が問題なのか?
・遺産分割ができない
・預貯金が下ろせない
・全遺産の名義変更ができない
相続人に「行方不明者」や「音信不通」の人がいた場合、遺産分割ができないため、金融資産を下ろすことも不動産の名義を変更することもできません。
例えば、親が相続税納税資金として貯めていた預金があったとしても、原則として相続人全員の実印が揃わない限り引き出すことができず、相続人自身が納税資金を調達しなければいけなくなります。また、納税用に確保していた不動産も名義変更しない限り名義変更することはできず、親の名義のまま誰かが固定資産税等を負担し続けなければならないのです。
さらに、遺産分割が整わない場合、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができず、未分割のまま申告し、高い相続税を負担することになってしまいます。
トラブルはこう回避する!
相続発生『前』なら・・・遺言書を作成する
時間をかけてその人を探すこともできますが、いつ相続が発生するか誰にもわかりませんので、遺言書を作成しておくことがベストです(公正証書遺言がのぞましい)。遺言書には遺言執行人を指定しておくと後の手続きがスムーズです。また財産に漏れがないような書き方にもしなければなりません。
相続発生『後』なら・・・家庭裁判所に申し立てをおこなう
行方不明者がいた場合は、家庭裁判所へ「不在者財産管理人の選任」を申し立て、同時に「財産管理人の権限外行為の許可審判」を申し立てることで行方不明者の財産を財産管理人に管理してもらう手が考えられます。ただし、不在者の法定相続分は手つかずの状態が継続するため、基本的な解決には至りません。さらに財産管理人は弁護士などの専門職が就く場合が多く、その場合、報酬等の費用もかかってしまいます。
失踪宣告を行う手もありますが、死亡とみなされるのは7年後です。
Posted by 行政書士金城勇事務所 at
11:14
│Comments(0)
自筆証書遺言について
2020年05月26日 / 遺言書について

前回のブログでは遺言書の意義と必要性について記載しましたが、今回からは遺言書の種類について説明します。
まず第一回目は自筆証書遺言です。
その前に、遺言書は大きく分類すると①普通方式遺言と②特別方式遺言の2つ分けられます。
①普通方式遺言
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
②特別方式遺言
死亡危急者の遺言
船舶遭難者の遺言
伝染病隔離者の遺言
在船者の遺言
①の方式は厳格な形式に則り作成されるものですが、もし皆さんが墜落する飛行機や沈没する船の中に居合わせたときなど、緊急を要する事態に陥った場合、遺言を遺すのに厳格な形式もへったくれもありませんよね。そのような場合に限り、要件を緩和した②の特別方式遺言が用意されているのです。しかしながら通常の日常生活の中で遺言をしようとする場合はやはり普通方式遺言の方式で作成しなければなりません。
それでは普通方式遺言の自筆証書遺言について詳しく説明します。
【自筆証書遺言】
特長
遺言者が財産目録以外の全文、日付・氏名を自書し、署名の下に捺印して作成する遺言です。簡単といえば非常に簡単ですが、方式を厳格に守らなければ遺言全体が無効になってしまいますので、その意味では細心の注意が必要です。
作成上の注意点は以下のとおりです。
筆記用具:鉛筆・万年筆その他、「自筆」できるものなら何でも結構です。ただし、変造等を防いだり、保存という面を考えると鉛筆は不適当です。
用紙:どのような用紙でも構いませんが保存に適した用紙を用いるべきです。
印鑑:三文判でもOKですが、偽造・変造を防ぐ意味から実印などきちんとした印鑑を用いるべきでしょう。
なお指印でもよいという最高裁の判例もでていますが、遺言書を開封するのは大抵が火葬を終えたあとになりますので、本物かどうか調べようにも火葬されたあとには調べる術がありませんので、指印は避けたほうがよいでしょう。
書式:書式は自由で、縦書きでも横書きでもOKですし、文字も判読可能であれば、日本語でも外国語でもOKです。ただし金額等重要な数字については「壱、弐、参、・・・」といった漢字を使ったほうがよいでしょう。
封筒に入れる必要はありませんが、封筒に入れて封印しておけば、死後、家庭裁判所での開封手続きをとる必要があるので、変造を防ぐことができ、また内容を秘密にしておくことができます。
全文自署:これが自筆証書遺言の一番のネックではないでしょうか。「遺言の全文」「日付」「氏名」は必ず全部自分で書かなければならないのです。
ただし法改正により、別紙で財産目録を添付する場合は、その「財産目録」に関してのみワープロ打ちや書類そのものを貼付することは可能となりました。その場合全ての財産目録に署名と捺印が必要となります。
その他、録音テープやビデオを用いた遺言書は無効です。
日付:これは非常に重要です。遺言が複数見つかった場合は後に書かれた方が優先されますので、遺言書の前後を決定するために、「特定の日」をきちんと自書しなければなりません。日付の記載がなかったり、「令和2年3月吉日」といった特定できない日を記載したり、また、日付印を用いたりすると遺言書全体が無効になってしまいます。
なお、判例では「還暦祝賀の夜」といった形でその日が特定できれば有効であると解されていますが、このような記載は避け、令和〇〇年〇月〇日と明確に記載するようにしてください。
氏名の記載:遺言者が誰であるか、他人と区別できる程度であれば十分ですので、「明石家さんま」でも「ビートたけし」などでもよいとされています。
長所と短所
長所
・簡単に作成できること
・自分一人で作成すればお金がほとんどかからないこと
・証人の立会いが不要なので遺言の存在と内容を秘密にしておけること
短所
・保管について注意しなければならないこと((ただし法改正により、令和2年7月10日より法務局での保管が可能となります)
・紛失や偽造のおそれがあること
・遺言の内容について要件の不備により無効となるおそれがあること
次回は公正証書遺言について説明します。
当事務所のオリジナルHPもご覧下さい
↓ ↓ ↓ ↓
行政書士金城勇事務所 ☜クリック!
 098-923-1447
098-923-1447 Posted by 行政書士金城勇事務所 at
09:59
│Comments(0)
遺言書を残そう
2020年05月26日 / 遺言書について
 皆さんは遺言書を書いた、もしくは見たことはありますか?
皆さんは遺言書を書いた、もしくは見たことはありますか?多分そうそう無いかと思います。沖縄で遺言書を遺している方はおそらく100人に1人くらいの割合ではないでしょうか。
現在70歳以下の方は法定相続(遺産相続配分が法律で定められている)世代ですが、それ以上の年代の方は家督相続(長男が全て遺産を相続する)世代と言われています。つまり「遺言書なんか書かなくても長男が相続するから問題ないよ」という考えがまだ存在しているため、遺言書を遺す習慣がないのです。
「子供たち全員仲がいいから私たちの家族は遺産相続で揉めることは無いよ」
残念ながら子供たちは相続で揉めないと思うのは幻想だと思ったほうが良いかもしれません。遺産の法定相続分を巡る争いは後を絶ちません。
「財産はほとんど無いから揉めることは無いよ」
違います。無いから揉めるのです。相続争いが訴訟まで発展するケースは遺産総額5000万円以下の家庭で実に75%を占めているのです。テレビのワイドショーでは大金持ちの相続争いが連日取り上げられており、一般市民には遠い世界の話に見えてしまいがちですが、お金持ちの方はある程度の偏った遺産配分が成されたとしてもそんなに揉めることはありません。一般市民だからこそ1円単位の遺産配分で揉めるのです。特に沖縄の方の財産は不動産が約7割以上を占めるといわれており、その不動産を法定相続分通りに分けることは不可能に近いため、争いが生じる可能性は極めて高いといえます。
「まだ元気だから、そのうち書くよ」
それでは自分が元気でなくなるのがいつなのかを知っている方はどれくらいいるでしょうか?元気でなくなったときに遺言書を書こうと思ってもできません。元気なときだからこそ遺言書を遺す必要があるのです。
ここ沖縄は、相続関係に関して独特の習慣が残っております。また軍用地所有者の年齢層が高くなってきており、その承継問題も進んでいません。また会社経営の承継問題も全国で一番遅れているといわれています。
これらを解消するには遺言書を遺すことこそが一番の特効薬です。
遺された家族が「争族」とならないために、遺言書を書いてみることをオススメします。
次回では遺言書の種類について説明していきます。
当事務所HPもご覧下さい
↓ ↓ ↓ ↓
行政書士金城勇事務所☜クリック!
 098-923-1447
098-923-1447 Posted by 行政書士金城勇事務所 at
09:46
│Comments(0)














