行政書士資格受験生あいちゃんの学習日誌:自筆証書遺言書の要件緩和 法務局での保管制度 手続編
2020年06月12日/ 遺言書について
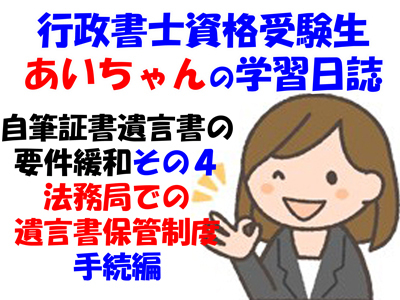

フハハハハ!お前ら盛り上がってるかーっ!!

お、おーー!!
(まだ続いてたのか・・・ ってかお前らって僕しかいないんですが・・・)

気合い入れていこうぜ ENJOY!

(おわっ!今日は一人二役なのか!)
イ、、イエーイ。。。
ってなことで、今回は前回の続きから【自筆証書遺言書の法務局保管制度:手続編】です。
前回は自筆証書遺言書の保管に関するデメリットをお話しましたが、今回の法改正でメリットが一つ増えたんですよ。

ほぉ、そのメリットとは?

はい、家庭裁判所の検認が不要になりました。
これまでは自筆証書遺言書を発見しても、勝手に開けることはできず、家庭裁判所に検認手続きを行って然るべき準備を行ったあと、裁判官と遺族と一緒に開封しないといけませんでした。
しかし今回から法務局という公的機関が保管することによって、偽造・改ざんの恐れがなくなったので、検認という手続きが要らなくなったんです。

煩わしい手続きが減って遺族もかなりの負担減だぜ!

そうですね。憔悴しきっている遺族にとっては、少しでも負担が減るのはとても助かります。
さて、ここからはQ&A形式で手続きについて説明していきます。
それでは質問どうぞ!

預けるのはどこの法務局でもいいのか?

遺言者の住所または本籍地を管轄する法務局か、遺言者の不動産が所在する法務局です。ただし全ての法務局で預かってくれる訳ではないので、事前に確認しましょう!

準備する書類とかはどんなのがある?

①遺言書
これは封筒に入れる必要はありません。また遺言書が2枚以上ある場合でもホッチキスで留める必要はありません。
なぜなら法務局では遺言書をスキャンして電磁記録として残しておく必要があるからです。
これまでの自筆証書遺言書の方式だと、封筒に入れて封印することなどが条件でしたが、これが全く必要なくなったということですね。
②申請書
法務省のHPでダウンロードできるので、事前に準備しておきましょう。また法務局の窓口にも備え付けられてますよ。
③本籍の記載のある住民票など
作成後3ヵ月以内のものを用意しましょう。
④本人確認書類
免許証やマイナンバーカードでOKです。
⑤手数料
保管の手数料は一通につき3,900円です。
収入印紙を買って申請書に貼り付ける形ですね。
これらを用意して事前予約を忘れずに行いましょう。いきなり行っても取り合ってくれませんよ!
その後手続きが全て終了したら保管証を受け取ります。
これには保管番号が記されており、その後の処理でいろいろと必要になりますので大切に保管しましょう。
遺言書を法務局に保管していることを家族に伝える場合にも、この保管証を利用すると便利です!

一度預けた遺言書の内容を、後日確認することもできるのか?

もちろんできますよ!
電磁記録として残されていますので、タブレット等のモニターで閲覧するのであればどの法務局でも確認ができます!
ただし原本を閲覧したいのであれば、もちろん預けた法務局に限られます。
モニターでの閲覧なら手数料は1,400円、
原本の閲覧なら手数料は1,700円です。

遺言書の変更や撤回も可能?

はい、できます!
撤回書又は届出書を事前に作成して、事前予約を行ってから法務局で手続きしましょう。

遺言者本人が病気等で法務局に行けないときは、代理人が申請してもOK?

残念ながら代理人の申請は認められておりません。
でも介助のために付添人が同伴するのはOKですよ!

この制度が始まる前に作った遺言書でも預かってくれる?

はい。遺言書の様式に問題がなければ保管申請可能ですよ!

遺言者が亡くなった後の手続きは?

手続きは上で説明したのとほぼ一緒です。
要望に応じた書類は全て法務省のHPでダウンロードできますので、事前に申請書を準備して法務局に出向きましょう!
と、だいたいこんな感じですね。
この法改正によって今後は自筆証書遺言書の作成を選択する方がかなり増えてくると思っています。
公正証書遺言の場合は、公証人が内容をしっかり確認してくれますが、自筆証書遺言書は内容をチェックするのが本人に限られてしまいます。ですのでこれまで以上に我々のような専門家のアドバイスが重要になってくるでしょうね。
以上で自筆証書遺言書に関する法改正の説明は終了です!
あいちゃんもしっかり勉強しましょうね!

はーい!

(あ、ちゃんと戻った!)
当事務所のHPもご覧ください!
行政書士金城勇事務所 ☜クリック!
 098-923-1447
098-923-1447Posted by 行政書士金城勇事務所 at 09:05│Comments(0)



















